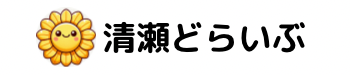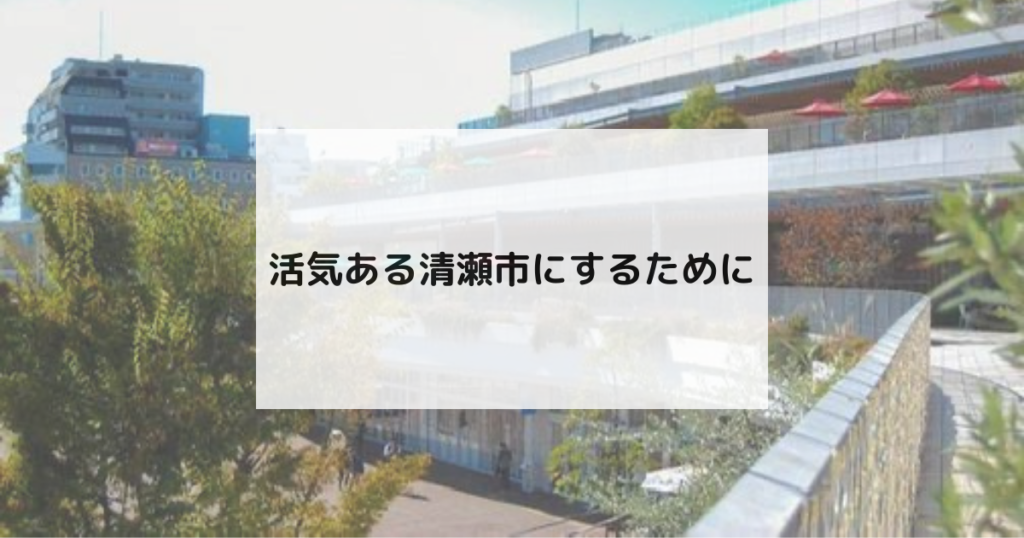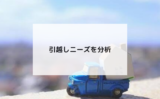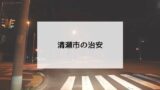清瀬市は人口がなかなか増えないこと課題です。特に20〜30代の人口が横ばいかやや減少している状況です。
市の魅力を高め、引っ越しの選択肢に浮上させるために、交通利便性や治安、自然環境の整備が必要です。
今回は活気ある清瀬市を実現するために何が足りないのか、私の見解を好き勝手書いていこうと思います。
清瀬市の年代別 人口推移
清瀬市の年代別 人口推移は以下の通りであり、全体的に横ばいか、やや減少傾向です。
| 20〜30代 | 40〜50代 | 60〜70代 | |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 15,357 | 21,717 | 17,682 |
| 2020年 | 15,489 | 21,824 | 17,556 |
| 2021年 | 15,499 | 21,931 | 17,379 |
| 2022年 | 15,460 | 21,954 | 17,163 |
| 2023年 | 15,453 | 21,870 | 17,071 |
活気作りの中枢を担う若者世代がなかなか増えないことが大きな問題に感じます。
実際、清瀬市の65歳以上の人口割合は、2020年実績で多摩地域中6番目に多い状態です。
清瀬市を活気ある街にするには?
少子高齢化が進む中、清瀬市も例外ではありません。将来にわたって持続可能な地域であるためには、若い世代を呼び込む必要があります。
本章では、新社会人や子育て世帯などの若年層にとって魅力的なまちづくりの方向性について、考察していきます。
新社会人の引越しニーズに応える

引越しのタイミングは、主に新社会人としての就職や、大学への進学時に集中します。
ただし、大学生は卒業後に就職先の近くへ引っ越すことが多いため、長期的な人口増につながるのは新社会人層と考えられます。
では、引越しを検討する人たちは、住まい選びで何を重視しているのでしょうか?
厚生労働省の調査によると、重視されているポイントは次のとおりです。
- 交通利便性の良さ
- 治安の良さ
- 自然環境の良さ
- 医療・福祉環境の充実
- 商業施設の充実
新社会人層をターゲットにする場合、ライバルとなるのは西武池袋線沿線の近隣駅です。
そこで、清瀬市に実際に住んでいる私の目線から、これらの項目について近隣駅との比較を交えつつ、率直な感想をお伝えします。
1. 交通利便性の良さ
清瀬市を通る西武池袋線は、東京メトロ有楽町線・副都心線、東急東横線などと相互直通運転しており、都心へのアクセスは良好です。池袋まで約20分のため、通勤圏として十分な距離感です。
ただし、近隣駅も同様に西武池袋線沿線にあり、比較すると利便性ではやや見劣りします。
たとえば、東久留米駅は通勤急行の停車駅、秋津駅はJR武蔵野線との乗換駅、所沢駅は全ての種別の列車が停車し、西武新宿線への乗り換えも可能です。
清瀬駅は急行が止まらず、乗り換え路線もないため、通勤や通学でのアクセス利便性では周辺駅に一歩劣るのが実情です。
この点については、行政の施策で直接改善するのは難しい部分です。
2. 治安の良さ
下表からもわかるように、清瀬市は東京都や埼玉県内でも比較的治安が良い地域といえます。犯罪件数は少なく、落ち着いた住宅街が多いのが特徴です。
| 犯罪率:人口1千人あたりの刑法犯認知件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬 | 東久留米 | 東村山 | 所沢 | 新座 | 東京都 | 埼玉県 | |
| 2014 | 8.83 | 10.31 | 9.55 | 11.17 | 11.10 | 12.04 | 10.62 |
| 2015 | 7.68 | 9.58 | 8.38 | 10.47 | 11.53 | 11.05 | 10.10 |
| 2016 | 7.96 | 7.92 | 7.38 | 9.10 | 11.15 | 9.95 | 9.52 |
| 2017 | 7.64 | 6.91 | 7.36 | 8.13 | 8.99 | 9.18 | 8.67 |
| 2018 | 6.88 | 6.64 | 5.28 | 7.29 | 8.28 | 8.33 | 8.19 |
| 2019 | 6.50 | 5.37 | 5.41 | 7.13 | 8.63 | 7.57 | 7.56 |
| 2020 | 4.85 | 4.76 | 4.07 | 5.61 | 6.27 | 5.98 | 6.06 |
| 2021 | 4.06 | 3.97 | 3.79 | 4.85 | 5.30 | 5.46 | 5.47 |
| 2022 | 5.27 | 4.71 | 4.71 | 4.84 | 5.27 | 5.67 | 5.72 |
ただし、近隣の自治体も同様に治安は安定しており、清瀬市が特別に優位とは言いきれません。
たとえば所沢市は駅周辺の発展に伴い居酒屋などの飲食店も多いため、やや犯罪率は高めですが、東久留米市や東村山市との間に大きな差があるとは感じません。
3. 自然環境の良さ
清瀬市は、緑豊かなまちとして知られています。市内には、特別緑地保全地域や緑地保全地域に指定された土地が多く、自然環境に恵まれています。
市全体に占める樹木地・草地・農地の割合(緑被率)は、近隣自治体と比べても高く、所沢航空記念公園や狭山丘陵などの広大な自然地帯を有する所沢市に次いで2番目。データとして見ても、清瀬市は確かに“緑のまち”といえるでしょう。
- 所沢市:43.0%
- 清瀬市:36.9%
- 東久留米市:29.2%
- 東村山市:26.3%
ただ、実際に暮らしていると、その自然の豊かさを強く実感する機会は、意外と多くはありません。
緑地保全地域は、本来「災害時の緩衝地帯」や「都市のヒートアイランド対策」「空気や騒音の緩和」として重要な役割を担っています。
しかし、散歩を習慣としない若年層にとっては、“ただ緑が多い場所”という印象に留まりがちで、ときに“少し田舎っぽい”と感じられることもあるように思います。
4. 医療・福祉施設の充実
結核療養地としての歴史的背景から、清瀬市には「国立病院機構 東京病院」をはじめとする大規模な医療機関が複数立地しており、地域医療体制は比較的整っています。
一方、大規模な医療機関の多くが慢性期型病院であり、若者層が求める病院とは少しギャップがあるのが実情です。また、清瀬市在住の私の実感として、建物の内外装が古いクリニックが多く、清潔感に欠ける印象もあり、やや田舎っぽさを感じることもあります。
とはいえ、引越しを検討している人にとって、「病院のまち 清瀬市」というネームバリューは十分なインパクトがあり、近隣自治体と比べても優位性のあるポイントであることは間違いないと思います。
5. 商業施設の充実
清瀬駅周辺には、スーパーやドラッグストア、飲食店など、日常生活に必要な商業施設がコンパクトに集まっています。特に、駅直結の西友や、南口にあるオーケーストアは、多くの市民にとって身近な買い物拠点です。
一方で、東村山市のイトーヨーカドー、東久留米市のイトーヨーカドー・イオンモール・クルネ、所沢市の西武所沢・グランエミオ所沢・エミテラス所沢などと比べると、清瀬市の商業施設はやや小規模で、専門店の数も限られています。
子育て世帯に優しい環境づくり

子育て世帯に優しい環境づくりは、新たな転入者の増加だけでなく、既存住民の転出防止にもつながる重要な要素です。
たとえば、清瀬市在住の社会人が結婚を機に住み替えを検討する際には、夫婦双方の勤務地へのアクセスだけでなく、保育園・幼稚園の充実度や医療体制、公園・自然環境など、子育てを取り巻く環境が大きな判断材料になります。
せっかく新社会人の転入が増えても、子育て環境が整っていなければ、結婚や出産を機に他の自治体へ転出されてしまう可能性があり、長期的な定住促進にはつながりません。
清瀬市に実際に住んでいる私の目線から、清瀬市の子育て体制について、率直な感想をお伝えします。
充実した子育て体制をもっとPRすべき
清瀬市は「子育てしやすい街」というイメージがあまり浸透していませんが、実際に暮らしてみると、子育て世帯を支える体制がしっかり整っていると感じます。
具体的には、以下の点で非常に魅力的です。
- 新規入園決定率が非常に高い
清瀬市は、新規入園希望者に対する保育園の入園決定率が非常に高く、全国的に見ても上位に位置しています。たとえば2023年には、東京都および埼玉県の全自治体の中で第3位、関東以外の自治体と比べても第2位という極めて高い数値を記録しました。 - 給付金や助成金が充実
清瀬市の児童手当、東京都の018サポートと医療費助成、国と都の出産・子育て応援ギフトなど、清瀬市では子育て世帯を支援する制度が幅広く整備されています。これらにより、育児にかかる経済的負担を大きく軽減することが可能です。
市民が受けられる子育て支援制度は、もっと積極的にPRすべきだと思います。
とくに清瀬市公式ホームページの子育て関連ページは、文字情報が多く視認性に欠けています。支給額や支給対象などの具体的な情報はともかく、支援の概要はイラストや図解を用いて1枚のチラシ形式で簡潔にまとめるなど、視覚的に伝わる工夫が必要だと感じます。
将来的には、東京都福生市のように『共働き子育てしやすい街ランキング』で毎年上位に選ばれるような市を目指せると理想的です。
実際、清瀬市(面積10.23km²、人口約7万6,000人)は、福生市(面積10.24km²、人口約5万6,000人)と規模も近く、ポテンシャルは十分にあると感じます。
個人的にあると嬉しい支援制度
前述の通り、清瀬市は東京都の補助も受けられるため、金銭面では非常に充実しています。
そんな中、実際に清瀬市で共働き生活を送る立場から、「こんな制度があればもっと助かる」と感じる支援について、いくつか挙げてみます。
- 認定こども園の拡充
認定こども園は、保育園(保育)と幼稚園(教育)の機能を一体化した施設で、共働き家庭には非常に便利です。しかし、現在はまだ十分な数がなく、3歳以降の転園を考える家庭も多いです。認定こども園を増やすことで、転園の手間を減らし、より一貫した保育が提供できるようになると良いです。 - 病児保育の拡充
子どもが急に熱を出したときなどに預けられる病児保育の施設が少なく、共働き家庭には大きな負担です。対応できる施設や枠をもっと増やしてもらえると安心して働けます。 - 延長保育料の助成
標準保育は18時までで、それ以降は追加料金が発生します。事前申請も必要なため、共働き家庭には使いづらい面があります。せめて19時までは助成によって無償化されると助かります(もちろん、保育士の労働環境への配慮も必要ですが)。
上記はいずれも実現には大きな財源を要するため、実行するのは非常に困難だと思いますが、いずれか一つでも実現できれば、清瀬市の魅力として外部に向けたPR材料になるはずです。
現実は財源がネック
子育て支援や若年層の定住促進に向けた施策には多くのアイデアがありますが、現実には“予算の壁”という大きな課題が立ちはだかっています。
清瀬市には大型商業施設や大手企業がほとんどないため税収が少なく、限られた財源の中で、どこにどれだけ投資するかの選択は非常に難しい問題です。
たとえば、『共働き子育てしやすい街ランキング』で毎年上位に入る東京都福生市と比較してみると、以下のような違いが見られます。
清瀬市
・面積:10.23km²
・人口:7万6,000人
・財政力指数:0.68
・一般会計予算(2024年度):343億9,200万
福生市
・面積:10.24km²
・人口:5万6,000人
・財政力指数:0.76
・一般会計予算(2024年度):355億4,000万円
両市の予算規模や面積に大きな違いはないものの、清瀬市は福生市よりも人口が約1.36倍多いため、一人あたりにかけられる予算は相対的に少なくなります(約0.74倍)。
もちろん、予算はすべて住民サービスに直接割り当てられるわけではなく、公共施設やインフラ維持にも使われるため単純比較はできませんが、財政面での厳しさが垣間見える数字と言えるでしょう。
私が求める清瀬市の将来像
自然・医療・支援がそろった
子育てしやすい街 清瀬
こんなキャッチフレーズで清瀬市をPRできたら、どれほど魅力的だろうと思います。

市内には雑木林や川沿いの遊歩道など、子どもたちが自然と触れ合える環境が多く残されています。また、結核療養地としての歴史的背景から、大規模な病院が数多く立地しているのも清瀬市の大きな特徴です。
さらに、児童手当や医療費助成、保育支援など、共働き家庭を支える制度を整えることで、「自然」「医療」「支援」という三本柱として整理・可視化できれば、清瀬市は子育て世帯にとってより魅力的な選択肢となるはずです。そして、若い世代の転入を促す大きな力にもなるでしょう。